日本の織物探訪伝統と技術の美
布帛(ふはく)とも言う「織物」。織り方には三種類あり、中でも「綾織」のツイルはソーイングをする方には身近な素材なのではないでしょうか。
今回はそんな織物についてご紹介します。日本には様々な伝統的な織物があり、それを知るだけでもハンドメイドの参考になるはず。ぜひ色々な日本の織物あれこれの特徴を、この機会に少し見ていきましょう。
そもそも織物とは?
織物とは、色染めした経糸と緯糸を組み合わせて作られる布地。染物とは違って、生地を織る前の糸を染めるため「先染め」と言われています。織り方には主に三種類あり、「平織」「綾織」「朱子織」が挙げられます。作り方は、織機に経糸を張り、その間に緯糸を通して作る製法が多いです。この緯糸の通し方次第で、どのような組織の織物ができるかが変わります。
織物の最大の特徴は、その頑丈さ。組織が非常に安定しており、洗濯後の伸び縮みも比較的に少なく、着ていても形状が大きく型崩れすることもあまりありません。そのため洋裁や和裁の布地として愛用する方も多いです。
日本の織物あれこれ
日本全国にはそれぞれの風土や地域性などを活かした様々な伝統的な織物があります。ここでは代表的な日本の織物の種類についてご紹介します。
結城紬(茨城県・栃木県)
茨城県結城市を中心に織られる、奈良時代発祥の絹織物。紬(絹織物の中でも非常に丈夫で庶民にも馴染み深い織物)の最高級品とも言われ、国の重要無形文化財にも指定されています。経糸、緯糸ともに真綿から引き出す手つむぎ糸を用い、手括りなどで絣糸を作り、「居坐機」という織り機で織る、伝統的な技法で作られています。非常に丈夫でありながら、緻密さも併せ持っている織物です。
黄八丈(東京都)
伊豆諸島の八丈島で織られてきた、歴史深い手織りの絹織物。光沢のあるしなやかな地と、鮮やかな黄色が目を引きます。色は黃、茶、黒の三色が基本ですが、媒染・糸の組合せ・織り方次第で様々な色を表現することも可能です。染めに用いる染料は、全て島内に自生する植物の天然染料。黄色はかりやす、茶色は「まだみ」の木の皮、黒は椎の木の皮から作られています。織りは手織り機による平織か綾織で、縞か格子の模様が多いです。
越後上布(新潟県)
新潟県南魚沼市に昔から受け継がれている平織りの麻織物です。盛夏用の着尺地で、麻織物の最上級品として知られています。柄は絣や縞が多く、薄手でシャリ感のある地風が特徴です。
牛首紬(石川県)
石川県の白山山麓で受け継がれてきた伝統的な紬。一般的な紬は繭を真綿にしてから糸を紡ぐのに対して、牛首紬は、二頭の蚕が一緒に作った繭「玉繭」を使い、繭から糸を直接引き出す方法で糸を採ります。高い技術で引いた太い糸で織る生地は、節の浮いたしっかりとしたすべりの良い質感と、光沢感があります。
西陣織(京都)
日本を代表する織物の産地、京都・西陣で生産される織物を総称したもの。錦、金襴、繻子、緞子などがあります。さまざまな技法を駆使して織り上げられた、色鮮やかで精密な模様が特徴です。明治期に紋織の機械を導入するなど技術の発展を続ける一方、昔ながらの手機の伝統も守り続けています。
博多織(福岡県)
生地に厚みと張りがあり、帯地としてよく使われる絹織物。鎌倉時代に宋から入ってきた唐織の技術が始まりと言われ、仏具の独鈷、華皿との結合模様の中間に縞を配した柄行の模様が特徴です。
本場大島紬(鹿児島)
奄美大島に自生するテーチキ(車輪梅)や泥を使った泥染めの技法により、独自の艷やかな黒や焦げ茶が表現される、本場大島紬。光沢のあるしなやかな地風が特徴です。奄美大島には他にも藍染の糸で織った藍大島、藍染と泥染併用の泥藍大島、多彩な色大島や白大島、薄地に織った夏大島も有名です。
久米島紬(沖縄県)
国の重要無形文化財に指定された沖縄県久米島で作られている紬。泥染めによる黒褐色や沖縄特有の絣模様が知られています。植物染料だけを使用したり、光沢や風合いを出す砧打ちなど、今も古い技法を受け継いでいます。
まとめ
有名な織物をご紹介しましたが、これはごく一部で、全国各地にはまだまだ地域性を活かした様々な織物が沢山あります。ぜひご自身の住む地域にも、伝統的な織物がないか探してみてはいかがでしょうか。それを活用したハンドメイドも味がありそうですね。
参考ページ
・ワゴコロ「織物とは?種類や歴史、日本各地の織物をご紹介」
・中川政七商店の読みもの「染物・織物とは。多様な種類と日本の布文化の歴史」
織物関連の書籍
もっと詳しく知りたいって方はぜひこちらも参考になさってください♪
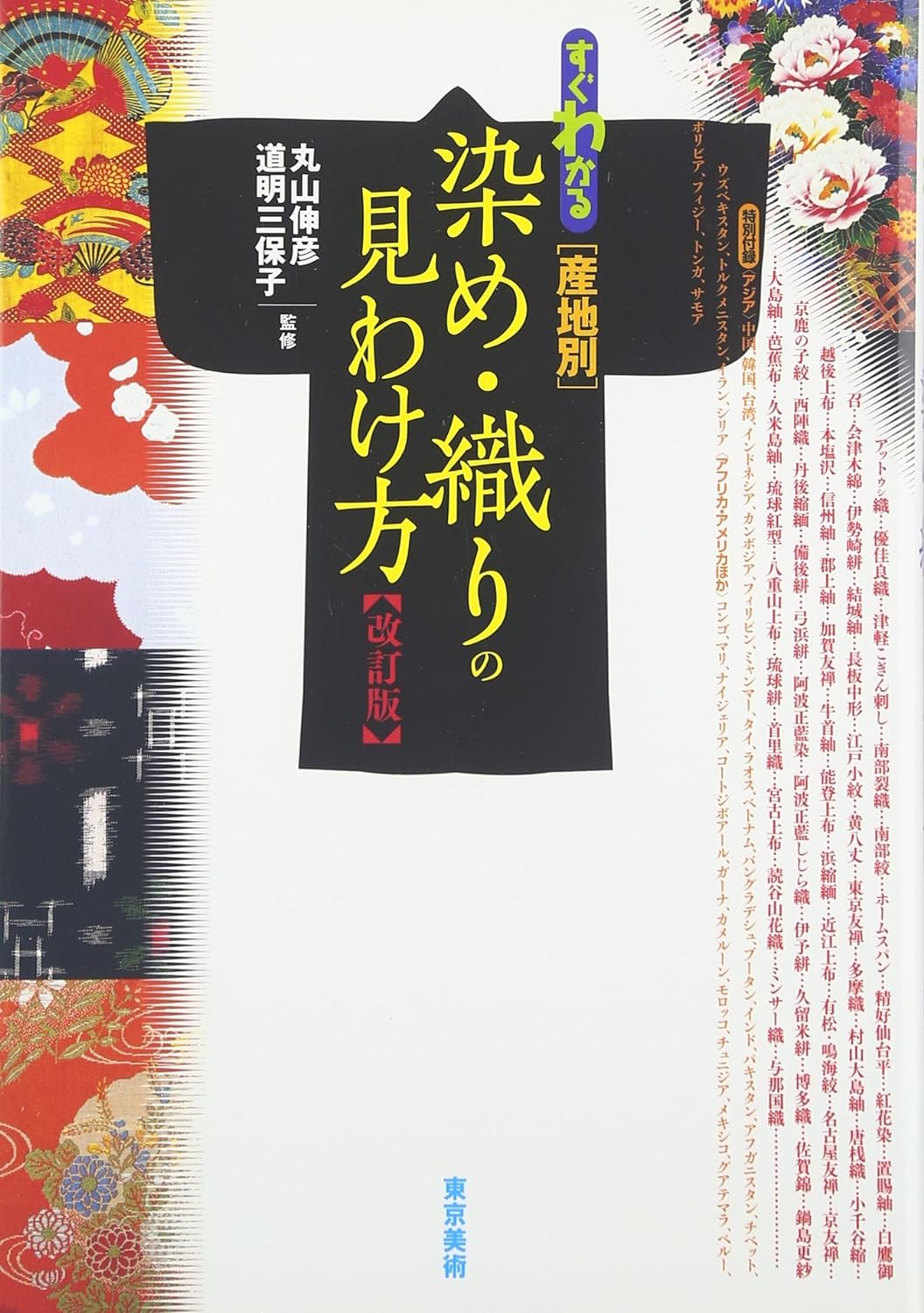
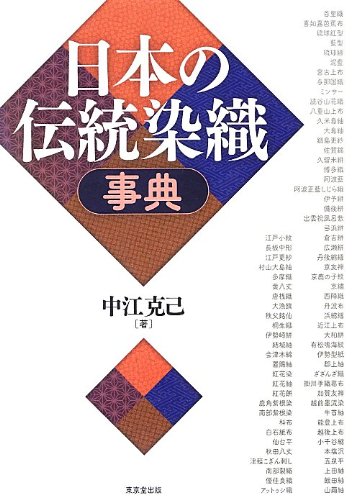
PERSON

プチプラで様々なハンドメイドをするのが好きなアラサー女子。ゴスロリ服の縫製にハマっている



![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a6bd945.a4a2f8d1.3a6bd946.82f5c268/?me_id=1213718&item_id=10000052&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkimonodokoro%2Fcabinet%2Fikou_20100329%2Fimg10621635749.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a6bd9a4.45b6e803.3a6bd9a5.421e0967/?me_id=1201556&item_id=10000270&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkusaya%2Fcabinet%2Fimg60790068.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a64575a.17b35753.3a64575b.faebf9f1/?me_id=1213310&item_id=20846093&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0197%2F9784286270197_1_3.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a6bdb4c.7a3ab447.3a6bdb4d.7e433ab7/?me_id=1286251&item_id=10000475&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fesuon%2Fcabinet%2F2019%2F12%2F11%2Fz.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a6bdbde.604c240a.3a6bdbdf.f452f184/?me_id=1407366&item_id=10107957&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fheiwaya%2Fcabinet%2Fracoon_23%2Fs4961_3.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)